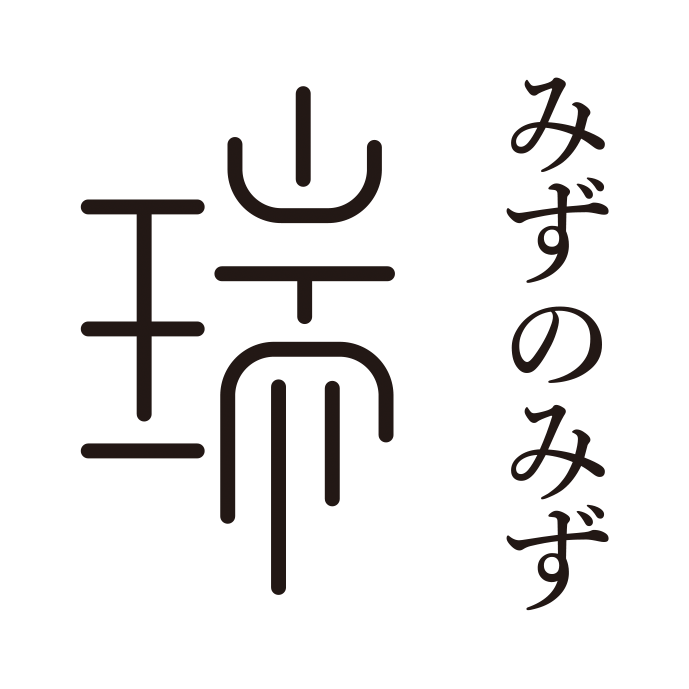News

FUNDINNOにて第2回クラウドファンディングを開始しました
【お礼とご案内】上限到達に伴い、オンライン事業説明会を中止いたします 2025年8月21日(木)にご案内させていただきました、FUNDINNOでの第2回株式投資型クラウドファンディングにつきまして、本日8月29日(金)をもって募集上限額に到達いたしましたことをご報告いたします。 多くの皆さまからのご支援・ご共感に、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。 これに伴い、今後予定しておりましたオンライン事業説明会の開催は中止とさせていただきます。 今後とも、引き続き、温かいご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 ———————————————————————————- いつも”みずのみず”を応援いただきありがとうございます。 本日、私たちみずのみず株式会社は、株式投資型クラウドファンディングプラットフォーム「FUNDINNO(ファンディーノ)」にて、2回目となるクラウドファンディングを開始いたしました。 Screenshot “水を選ぶことが、未来をつくることにつながる”そんな想いからスタートした”みずのみず”は、日本の水資源を守るというミッションのもと、上質な天然水の開発・販売を通じて、持続可能な社会への貢献を目指しています。 今回の資金調達は最大3,400万円を予定しており、調達資金は人材採用・イベント出展・商品開発および製造に活用し、さらなる事業成長を目指します。 株主優待について 弊社では、株主の皆さまに日本の天然水”みずのみず”を株主優待としてご提供いたします。保有株数に応じて、年間を通じて商品をお届けいたします(既存株主様も対象となります)。 ——水を株主優待に”みずのみず”ならではの取り組みです。 投資家向け説明会の開催 クラウドファンディング開始に先立ち、事業の現状・今後の戦略についてオンラインにて直接ご説明する投資家向け説明会を開催いたします。 弊社代表より、事業のビジョン、成長戦略、株主優待の詳細についてもご案内いたします。 具体的な日時やオンラインURLについては下記ご参照ください。 みずのみず株式会社 株式投資型クラウドファンディング実施 及び オンライン事業説明会開催のお知らせ 今後のスケジュール•8/21(木) 情報開示 12:00-•8/23(土) 募集開始 10:00-•9/2(火) 募集締切 -23:59 FUNDINNO 募集URL:https://fundinno.com/projects/689 より大きな事業拡大に向け、弊社一同が一丸となって、踏ん張りと、更なる躍進の年と位置付けて邁進して参ります。これからも更なるご支援、ご協力の程、何卒、よろしくお願い致します。...
FUNDINNOにて第2回クラウドファンディングを開始しました
【お礼とご案内】上限到達に伴い、オンライン事業説明会を中止いたします 2025年8月21日(木)にご案内させていただきました、...
続きを読む
“水”の種類について
同じ水でも、体が求める水は一人ひとり違う 私たちは日々、当たり前のように水を飲んでいます。コンビニで買うペットボトルの水、家の蛇口から出る水道水。どれも透明で、無色無臭。あまり深く考えずに口にする人も多いのではないでしょうか。 けれど、私にとって「水」は、単なる飲み物ではありませんでした。 子供の頃、私はごく普通の水を飲みたがらなかったそうです。親は苦労して試行錯誤を重ね、「純水」というミネラルや成分をほとんど含まない水にたどり着きました。そのときの私は、それまでとは比べものにならないほどの勢いでゴクゴクと飲み、私のアレルギー体質だった体も落ち着いていったといいます。 この時の私は、きっと“体に合う水”を本能的に知っていたのかもしれません。この話を聞いたとき、私ははじめて、必要としている水はみんな同じではない、人それぞれ、求めている水は違うのだと気づきました。 それぞれの「天然水」の役割 “みずのみず”で活動をするようになってから、その感覚はますます強くなりました。一口に「天然水」と言っても、その性質には大きな幅があります。 たとえば、ナチュラルウォーター※1と呼ばれる水は、ミネラル分が少なく、味がやわらかいのが特徴です。煮物や出汁のように、繊細な風味を丁寧に生かしたい料理に向いており、素材の味を邪魔しません。また、調乳にも使われることが多く、赤ちゃんや高齢者にも安心して勧められる水です。 一方、ナチュラルミネラルウォーター※2は、地下を長く通る過程で自然のミネラル分をしっかり取り込んでおり、味にコクや厚みを感じることができます。スポーツ後のミネラル補給や、香辛料や油を使った料理との相性も良く、体を動かす人や健康意識の高い人にとって実用性の高い水です。 こうしてみると、「天然水」という言葉の裏にも、飲む人の体質や目的に合わせた適材適所があることがわかります。 ※1ナチュラルウォーター特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わない水です。ミネラル分はナチュラルミネラルウォーターよりも少ない傾向があります。 ※2ナチュラルミネラルウォーターナチュラルウォーターの中でも、地下でミネラルが溶け込んだ水を指します。ナチュラルウォーターと同様に、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の処理は行いません。ミネラル分が豊富で、地層を通る過程でミネラルが溶け込んだ水です。 “水”の選択 市販されている「ミネラルウォーター」と表示された水の中には、複数の水源をブレンドしたり、ミネラル成分を調整したりしているものもあります。こうした水は、安定した成分バランスが特徴で、整腸作用や栄養補給の目的で選ばれることがあります。 ただし、硬度が高くなると苦味や重さを感じやすく、胃腸が敏感な人には負担となることもあります。私のように、体質的に水の成分に影響を受けやすい人にとっては、こうした違いが体調に直結する場合もあります。 そしてもう一つ、私の原点でもある「純水」は、H₂O以外の成分をほとんど含まない“まっさらな水”です。味もにおいもほとんどなく、コーヒーやお茶など素材本来の風味をしっかり引き出したいときにはぴったりです。赤ちゃんのミルク作りや薬の服用、アレルギー体質の人が安全に水を飲むときにも、純水が最適だと思います。 私にとっては、この純水こそが「水が命を支えてくれる」という実感を与えてくれた水でした。すべての人に純水が必要なわけではありません。でも、誰にでも“その人に合う水”は、きっとあると思います。 水は、「体が求めているもの」を映す存在 水を選ぶとき、「なんとなく飲みやすいから」「とくにクセがないから」と感覚で選ぶ人が多いかもしれません。けれど、水の種類ごとに性質が異なり、飲む人の体質やライフスタイルに合う・合わないがあることを知っておくだけで、選び方は大きく変わってきます。 料理やお茶のために、できるだけ成分を感じさせない水を使いたいときにはミネラルの少ない軟水が合っていますし、日常的に体を動かす人や汗をよくかく人には、ミネラル分を含んだ中硬水〜硬水が実用的です。そして、成分による負担を避けたい人や、素材そのものの味を丁寧に引き出したい人には純水が向いています。 「どの水が一番良い水か」ではなく、「自分にはどんな水を必要としているのか」その視点で水を選ぶことができれば、日々の体や暮らしを整える確かな味方になってくれるはずです。 私が赤ん坊の頃に体で選んでいたように、今の自分もまた、体の声を聞きながら水を選んでいきたい。そう感じています。

みずのみず株式会社 株式投資型クラウドファンディング実施 及び オンライン事業説明会開催のお知らせ
みずのみず株式会社はこのたび、株式会社FUNDINNOにて、「株式投資型クラウドファンディング」による資金調達を実施することとなりました。 Screenshot 募集ページ 募集ページURL:https://fundinno.com/projects/689 つきましては、下記日程・要領にて今回の募集に関するオンライン事業説明会を実施させて頂きます。本件にご興味がおありになる方は、この機会にぜひご参加頂き、弊社及び弊社が実施する今回の募集についてのご理解を深めて頂ければ幸いです。 -記- 株式投資型クラウドファンディング説明会 弊社及び弊社事業の内容について代表取締役より解説したのち、皆様から頂いたご質問に対して、直接その場でお一人ずつ、丁寧にご回答させて頂く説明会になります。 日程 8/23(土)10時~11時 8/24(日)19時~20時 8/25(月)19時~20時 8/30(土)10時~11時 8/31(日)19時~20時 9/1(月)18時~19時 9/2(火)18時~19時 説明会会場URL 全回共通リンク: https://meet.google.com/tnf-jmec-eos ※Google meetでの開催 FUNDINNOへの投資家登録はこちら https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=b4vpeikj2y ※弊社への50万円以上の投資に興味を持ってくださった方は、弊社お問い合わせフォームまたは株式会社FUNDINNO公式サイトにお問い合わせください。株式会社FUNDINNOにお繋ぎします。 注意事項 ※発言等は主催者が指名した際のみでお願いいたします。 ※上限募集金額を達成した場合や急なトラブルなど、予告なくオンライン事業説明会が中止・日時変更になる場合がございます。 ※FUNDINNOの募集ページに記載しております開示情報は、FUNDINNO投資家登録されている方しか閲覧できない情報もございますので、本オンライン説明会内では共有できない内容がございます。ご質問等には個別に回答させていただくか、FUNDINNOへのご質問の解答欄に回答させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 ※画面オフの参加でも問題ございません。発言時以外はミュートにてお待ちください。 ※急な開催となったため少人数でのご参加を見込んでおりますが、ご参加人数によっては皆様との意見交換などができない場合がございます。 ※Google...
みずのみず株式会社 株式投資型クラウドファンディング実施 及び オンライン事業説明会開催のお知らせ
みずのみず株式会社はこのたび、株式会社FUNDINNOにて、「株式投資型クラウドファンディング」による資金調達を実施することとなりま...
続きを読む

株主優待について
弊社では、株主の皆様のご支援に感謝するとともに 弊社商品をお楽しみいただくための優待サービスを提供しております。 【優待の基準日】 毎年10月末日 【優待内容】 ○111株以下 3本ご提供(対象製品:19:03) ○112〜167株 24本ご提供(対象製品:19:03) ○168〜223株 24本ご提供(対象製品:06:01) ○224〜279株 48本ご提供(対象製品:06:01・19:03 各24本ずつ) ○280〜559株 72本ご提供(対象製品:05:15・06:01・19:03 各24本ずつ) ○560〜1,119株 毎月24本ご提供(対象製品:06:01、期間:3ヶ月間) ○1,120〜1,679株 毎月24本ご提供(対象製品:19:03、期間:3ヶ月間) ○1,680〜2,239株 毎月48本ご提供(対象製品:06:01・19:03 期間:3ヶ月間) ○2,240〜2,799株 毎月24本ご提供(対象製品:19:03、期間:1年間) ○2,800〜5,599株 毎月24本ご提供(対象製品:06:01、期間:1年間) ○5,600株以上 毎月48本ご提供(対象製品:06:01・19:03...

幻のソムリエが語る「硬水と軟水の硬さと丸さが描く国の文化の違い」
水には、硬水と軟水という違いがあります。その違いは、単に舌触りやミネラルの含有量にとどまりません。食との相性、香りの感じ方、さらには文化や美意識にまで関わっているとしたら、どうでしょうか。 そんな水の奥深い世界を教えてくれたのが、幻のソムリエとして知られる吉田岳史さんです。今回のコラムでは、吉田さんとの対話を通して、硬水と軟水の性質がどのように国の文化と結びついているのかを、自身の体験を交えながら考察していきます。 「丸く柔らかな水」の感性 私が生まれ育った日本では、軟水が一般的です。日本の水の多くは、硬度が50mg/L未満の「軟水」「超軟水」に分類されており、そのまろやかさが特徴です。 (WHO(世界保健機関)の基準では、硬度が0~60mg/l 未満を「軟水」、60~120mg/l 未満を「中程度の軟水」、120~180mg/l 未満を「硬水」、180mg/l以上を「非常な硬水」といいます。) このような水は、お茶や出汁のような繊細な味を引き出すのに適しており、料理においても主張しすぎず、そっと素材を引き立ててくれます。 吉田さんは、そうした日本の水を「映し出す水」と表現しました。素材の味をそのまま映す鏡のような存在であり、決して素材の前に出ることはありません。この在り方は、日本文化にある“控えめさ”や“調和を重んじる心”とつながっているように感じました。 私が感じた「芯のある水」 私は幼少期を中国・長春で過ごしていた経験があり、そこでは水は必ず沸かして飲んでおり、日本の水とは違う重みやミネラル感を舌に感じていた記憶があります。調べてみると、中国の水の硬度は100〜300mg/Lの「中硬水」「硬水」が多く、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルを豊富に含んでいることがわかりました。 中国の食文化は、火を通した料理と香辛料を多用した味付けが特徴です。そうした強い味の料理に調和するには、水にもある程度の“芯”や“押し返す力”が必要になるのではないでしょうか。水が料理の背景に溶け込むのではなく、ときに共鳴し、ときに張り合う存在になる。それは、水も文化の一部として選ばれ、育まれてきた証なのかもしれません。 水に「尖り」と「上昇」を求める文化 フランスでは、硬度の高い水が好まれています。 吉田さんはフランスの水を「香りの尖り」「上昇する水」と表現していました。フランス文化の背景には、キリスト教の「魂は死後天に昇る」という思想があり、それが建築や芸術に反映されています。たとえば、ノートルダム大聖堂などに見られるゴシック建築の尖塔は、天へと向かう象徴です。 硬水もまた、香り高く、刺激があり、精神性すら感じさせる存在であることが好まれています。柔らかい軟水は「味がない」とされることもあり、多少クセがあっても“尖っていること”に美を見出すのがフランスらしさなのです。これは、香水、チーズ、ワインなどの「香りや刺激を愛する文化」とも共通しているのではないでしょうか。 音楽文化と水 チェコでは、ピルスナー・ウルケルに代表されるように、硬度の高い水でつくられたビールが親しまれています。吉田さんによれば、チェコのお客様の多くが「氷のようなカチッとした硬質なミネラル感」を好む傾向にあるそうです。硬水で造られるチェコのビールには、味の芯が感じられるそうです。 さらに吉田さんは、水のミネラル感が音楽の感性ともつながっているのではないかと語ります。たとえば、チェコ・フィルハーモニー管弦楽団の演奏には、どこか冷たく、硬く、シャープな響きがあると感じるそうです。水と音楽という一見異なるものの間に、感覚的な共鳴があるという視点はとても興味深いと感じました。 科学的に明確な因果関係を証明するのは難しいかもしれませんが、文化を形づくる“感性の層”の中で、水が担う役割は確かに存在しているのではないでしょうか。 文化が水を選び、水が文化を映す こうして見てみると、水は単なる飲料ではなく、文化を映し出すレンズのような存在だと感じます。 ・日本の水は、「柔らかさ」と「調和」を重んじる文化と共鳴します。 ・中国の水は、「強さ」や「芯」をもった食文化を支えます。 ・フランスの水は、「香り」や「上昇する精神性」を帯びています。 ・チェコの水は、「冷たさ」や「硬さ」を美として捉えています。どの水が「美味しい」と感じられるか、水を選ぶ時に注目する点は、その人が育った文化の価値観と密接に関わっています。文化が水を選ぶのか、水が文化を育てるのか。その答えは一つではありませんが、いずれにしても水は、目には見えない文化のエッセンスを映し出していると私は考えます。
幻のソムリエが語る「硬水と軟水の硬さと丸さが描く国の文化の違い」
水には、硬水と軟水という違いがあります。その違いは、単に舌触りやミネラルの含有量にとどまりません。食との相性、香りの感じ方、さらには...
続きを読む

日本の天然水ブランド”みずのみず”、 ラグジュアリー市場への本格展開へ
国内外の現場を知るプロフェッショナルと次なる挑戦へ みずのみず株式会社(本社:静岡県富士宮市、代表取締役:小寺 毅)は、ホテル業界において長年にわたり国内外のマネジメントに従事してきた田中正男氏(株式会社スプリント 代表取締役社長)を、8/1付で新たに顧問として迎えたことをお知らせいたします。今回の就任を機に、当社はホテルや航空会社といったラグジュアリー領域への本格的な展開を進め、ブランド価値のさらなる向上を目指してまいります。 “水”と“おもてなし”の親和性に着目し、共鳴から顧問就任へ 田中氏は、東京ヒルトンでの営業職を皮切りに、シンガポール、台湾、ロシア、フィジーなど海外複数拠点で総支配人を歴任。国内でも沖縄の高級リゾート運営など、長年にわたりホスピタリティの現場を牽引してきました。 そんな田中氏が“みずのみず”と出会ったのは、代表・小寺との沖縄での縁がきっかけでした。「世界一の水ブランドを目指しているという話を聞いて、小寺さんのそのまっすぐな思いに、何か自分の経験が役に立てるならと、自然に気持ちが動きました。実際にお水を飲んで、その美味しさに驚きましたし、小寺さんの誠実で信頼できる人柄にも強く惹かれました」(田中顧問) 日常に寄り添う“水”だからこそ、上質であることに意味がある 田中氏は、”みずのみず”との相性が良いシーンについてこう語ります。「朝の目覚めや一日の終わりに、身体をすっと通り抜けるような感覚があって、他の水とは明らかに違うと感じました」(田中顧問) 田中氏の就任により、今後はホテル・ウェルネス施設・航空会社など、上質な体験価値が求められる業界への展開を一層加速していく予定です。「まずは、日本一愛される水ブランドを目指して。これまで私が出会ってきた素晴らしい仲間たちとのご縁を活かしながら、必要とされる場所にこの水を届けていきたいと思っています」(田中顧問) 田中 正男(たなか まさお)株式会社スプリント 代表取締役社長 1961年大阪府生まれ。法政大学経営学部卒業後1984年東京ヒルトン入社。その後、シンガポール、台湾、ロシア、フィジーのホテルで総支配人を歴任。2013年にKPGホテル&リゾート沖縄統括支配人、2015年に 同社取締役社長に就任。2024年ユニマットグループ南西楽園リゾート常務取締役を経て、2025年7月に株式会社スプリントを設立し現職。 【みずのみず株式会社について】 “みずのみず”は、水を選ぶという行為そのものが、未来を守ることにつながるという信念のもと、日常に寄り添う上質な天然水を届けるブランドです。 日本各地の貴重な水源を守りながら、環境への配慮と美味しさの両立を追求。バナジウムやシリカといった天然ミネラルの高い天然水や、高濃こう度酸素を含有させた機能加工水を軸に、ホテル・サロン・空港ラウンジなど、厳選されたシーンでの展開を進めています。 私たちは、水の選び方を通じて、日常の質を高めるだけでなく、水の未来も守っていきます。
日本の天然水ブランド”みずのみず”、 ラグジュアリー市場への本格展開へ
国内外の現場を知るプロフェッショナルと次なる挑戦へ みずのみず株式会社(本社:静岡県富士宮市、代表取締役:小寺 毅)は、ホテル...
続きを読む