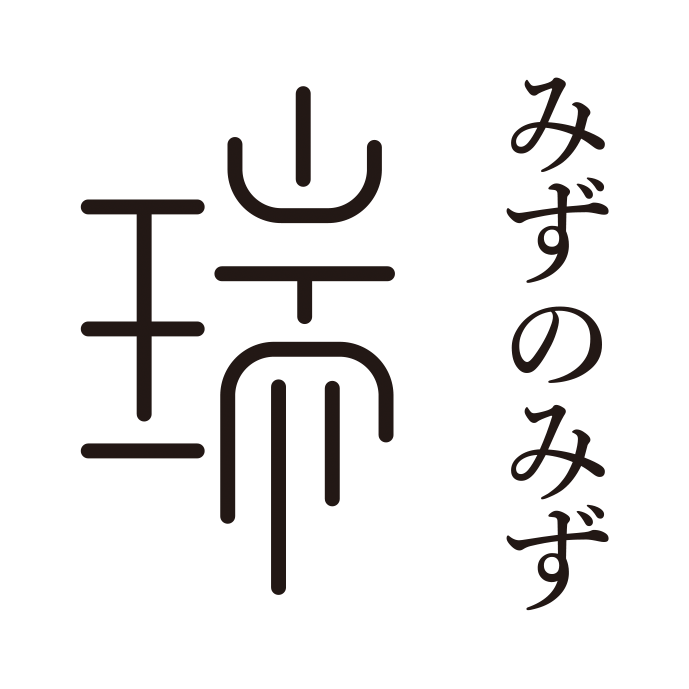日本では蛇口をひねれば安全な水が飲めることが当たり前であり、「水」に特別な価値を感じることは少なかったかもしれません。しかし今、世界では水に対する価値観が大きく変わりつつあると考えます。特に天然水は、テクノロジーの進化や産業の発展によってその希少性が高まり始めているのではないでしょうか。
人工的に作られる水と、天然水の違い
近年、海水を淡水化する技術や、水を再利用する技術が進化し、世界中の水不足地域で活用され始めています。たとえば中東やシンガポールでは、こうした技術によって「水の確保」がある程度可能になっています。日本でも、災害時や備蓄用に「人工的に作られた水」が注目されるようになりました。
たしかに、このような技術は人々にとって安心を与える存在ですが、一方で「天然水とは何が違うのか?」という視点はまだまだ浸透していません。
天然水は、長い年月をかけて地層を通り、自然にろ過された水です。その過程で、土地特有のミネラルが含まれ、地域ごとに異なる「味わい」や「成分」が育まれます。一方、人工的に作られた水には、こうした自然由来の栄養素がほとんど含まれていないことが多く、今後人間の体にどう影響するのか、まだ解明されていない部分もあります。
天然水を取り巻くもう一つの問題:産業による消費
さらに注目すべきは、天然水が産業によって大量に使われているという現実です。特に日本では、近年半導体工場の建設ラッシュが続いており、それらの工場では超純水と呼ばれる極めて純度の高い水が大量に使用されています。
1つの工場だけで、1日に20万トンもの水を使うケースもあり、これは67万人の1日分の生活用水に相当します。もちろん、こうした工場は経済成長を支える重要な存在ですが、その裏で天然水の消費が進んでいることにも目を向ける必要があります。
希少資源としての天然水
近年、日本各地の水源地が海外資本によって買収されるケースが増えています。水源地の買収は単なる土地取引ではありません。日本の持続可能な水供給に関わる重要な問題です。
実際に、私の父が所有する水源地を買収したいと海外の方が尋ねてきたことがありました。そのとき初めて、「日本の水資源が本当に狙われている」と実感しました。そして同時に、日本の水は世界的に見ても価値の高いものであることに気づいたのです。
これからの水の未来を考える
今や、飲料水は技術によって"作る"ことができる時代です。でも、天然水は「時間」と「自然」が作り出す、かけがえのないものです。人工の水で代替できる部分もあるかもしれませんが、それだけでは見落としてしまう価値が、天然水にはあります。
これからの時代、水はただの生活インフラではなく、文化や地域性、そして健康を支える“資産”として捉える必要があると私は思います。そして、日本の天然水の価値に、多くの人が気づき、関心を持つことが日本の貴重な水資源を守る第一歩になると私は考えます。